| 8月8日は写真家・星野道夫の命日で、彼は1996年、カムチャッカ半島・クリル湖畔にて、ヒグマに襲われ逝去した。四十代半ば、あまりに早い彼岸への旅立ちであった。 生前、おりに触れて、星野道夫が名作と称えていた、【極北の動物誌】ウイリアム・プルーイット著(1967年):岩本正恵訳が、昨年の秋、新潮社から刊行された。 この本に編集されている【旅をする木】という心地良い響きを放つ一説は、星野道夫が自身の著書のタイトルに引用したことでも、よく知られている。 『かつて亜北極のタイガに高くそびえていたトウヒの大木は、いまやこぶだらけのねじれた根のかたまりが残るだけになった。 −−−略ーーー トウヒは姿を変え、人間が幾世代移りかわっても存在しつづけるだろう。匂いづけの目印として、家の材木として、ウミヤックの骨組みとして、木の実を採るしゃくしとして。 いつの日か根のかたまりは腐るだろう。家の材木も、ウミヤックの骨組みも、そのほかのものも、いつかはたきぎとして燃やされるだろう。 炭素、水素、水、そのほか木を構成していた物質は大気に放出され、やがてふたたび結合して、いつの日かトウヒの若木として甦るかもしれない』ーーー【旅をする木】ウイリアム・プルーイット著:岩本正恵訳より
以下、あらましを記すと、 『アラスカの大地の一隅、一本のトウヒの梢から、ナキイスカの食べこぼした一粒の種子が落ち、その種子が芽吹く。やがてトウヒの若木は大木に成長した。 イスカの群や、アカリス、カナダカケス、ツグミ類、キンメフクロウなど数多くの野生たちが、何世代にもわたりこの木をねぐらに暮らし、子孫を残す。 極北の大地を刻むチェナ川は年々氾濫を繰り返しながら、トウヒに近づいた。ある年、氷解したチェナ川の奔流がトウヒを倒し、大木は海に押し流されてしまう。 トウヒは流木となり、アラスカ沿岸を漂つづける。夏が過ぎ、秋が過ぎ、冬が過ぎ、季節は巡り、春の激しい南風で海岸に打ち上げられた大木は、横倒しではあるが再び根を地中にさすと、少々の嵐ではびくともしないツンドラのオブジェに生まれ変った。 ツンドラに横たわる大木は、遠くからでもよく見えた。ホッキョクギツネが匂いづけをする。その足跡をたどり、エスキモーが罠を仕掛け、何匹もキツネを捕った。 エスキモーの猟師が亡くなると、若者がその木を切り、家を建る材木に用い、自然にカーブした木目を生かしてウミヤックのキールを作る・・・・・・・・・』 【旅をする木】を読むと、輪廻転生、大自然の悠久の時間(とき)の流れが思われる。 『一樹の陰一河の流れも他生の縁』・・・・・・とか。無意識のうちに仏教思想の中で生きる日本人には、なにかしら共感を覚える内容ではないだろうか、そんな印象をもった。 星野道夫は、この作品をベースに、写真絵本【旅をする木】を構想していたと云う。 私は、この物語から、それぞれが生かし生かされる多様な自然の営み、循環する生命の尊さ、豊かな自然の恵みなどを想い描いている。 宮沢賢治の童話の世界にも学びつつ、人と自然とのかかわりを、熊棚・くまだな風味の絵本(紙芝居)にまとめることができたなら、嬉しい。 うまくすれば、自然保護べんきょう会の、新しいテーマに仕上がるかもしれない。 |
【熊棚・くまだなの会】の最新情報、詳しい活動内容は |
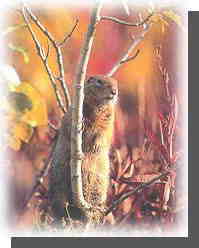 【アラスカ風のような物語】 星野道夫写真集より |
『自然の森は、その移相から草木類、陽樹、陰樹、そして極盛相へと長い年月をかけて循環する。それを人工的に持続的に理想的なかたちで実現するとすれば、どんな方式が考えられるだろうか。 小団地のモザイク的な【切り替えの森】が一番理想的ではないかと思われる。たとえば広葉樹林を伐って全部スギにする代わりに、この斜面は下の方をスギにして上は広葉樹林を残しておくとか。この谷の流域を広葉樹林にすると次の谷は針葉樹林というような恰好で、自然林と人工林を一対一にする程度で維持して行くやり方が望ましい。 自然にほうってある森林と、人間が管理した林では、生物的なバランスからいえば文句なしに自然のままが優れている。自然林のパーセンテージは相当量なければならない。 その上で人間が十分計画どおりに管理できる部分、たとえばあまり高い山の上などではなくて地形的にも十分管理ができ、経済的にも安全な範囲で成り立つところで林業経営が行なわれる必要がある。そうでない部分は、林業的経営は止めてそのままにして置いた方が良い』 ーーー【生態学からみた理想的森林】吉良竜夫著より |
今年は十年ぶりの冷夏でした。全国的に、お米の作柄は不良になるそうです。こういう年回りには山の木の実も不作となり、エサ不足から野生動物たちが里に降りてくる機会が増えます。 心配は、山里の人々と野生生物との間でさまざまな衝突が起き、お互いが哀しい結末を招いてしまうことです。少しでも、そういった不幸を避けるため、私たちは高山帯に設けたエサ台へドングリを運びます。 先日、上野市(三重県)の上野市立衣那古(いなこ)小学校、井上先生から電話がありました。 三重県環境部・野生生物グループ主催の『野生生物保護啓発ポスターコンクール』の応募作品に、 【熊棚・くまだなの会】の連絡先を書いてくださるそうです。ほんとに、ありがたいことです。この機会に、また新しい、ドングリ拾いの輪が広がると嬉しく思います。 ***************************************************** 【天高し空なるこころ石畳】ーーー百画 中世の参詣道、熊野古道の世界遺産登録に向けた運動が活発に行なわれています。新聞各紙の報道も、徐々にヒートアップしているようです。 数年前、東紀州の天狗倉山(てんぐらさん)と便石山(びんしやま)を訪ねました。 その折、天狗倉山の山頂で居合わせた方から、熊野古道補修ボランティアの話を伺いました。石畳の古道を、あるがままの姿で次世代に伝え残すという、その地道な活動に胸打たれました。世界遺産云々が、世間で大きな話題になる以前のことです。 中高年を中心に、古道ハイキングが大変な活況を呈していますが、ゴミ放置、野草採集、田畑への侵入などなど、心ないハイカーのマナーの悪さは、まったくもって情けないばかりです。これからは世界遺産観光ブームの大津波からも、古道周辺の自然環境を守ってゆかなければなりません。 厳しい見方をする人は、私たちがその地を歩むだけで、すでに自然を傷めていると言います。自然から恩恵を授かって成り立つ人間の営みなら、私たち、ひとり一人にできることで、自然へ何がしかのお返しをする、そういった心持が大切ではないでしょうか。 |