| 屋久島を一周、ぐるりと巡ったあと、宮之浦の屋久島環境文化村センターに寄った。宮之浦港の入り口に建つ竣工まもない真新しい建物だ。館内の小奇麗なトイレを拝借し、見学させて貰う。 有料スペースと無料コーナーに分かれおり、無料コーナーでは屋久島の植物写真展が開催されていた。写真撮影の許しを得、一点一点パネルを撮影させて戴いた。珍しい屋久島固有の植物の数々が丁寧な説明書きと共に、展示されていた。 2000.11.26 |
| サクララン (ががいも科) |
ヤクシマギボウシ (ユリ科) |
ミヤマムギラン (らん科) |
ヤクシマダイモンジソウ (ゆきのした科) |
 |
 |
 |
 |
| 九州南部を北限とする熱帯系の植物。鹿児島では少ないが屋久島の低山地では至る所に多い。 林内の岩や木に絡まり、肉厚の葉だけで観葉植物となる。 花は6〜9月頃、白く中央部が赤い星形の小花が多数集まって咲き、半球状となって美しい。 一度、花床ができると翌年も同じ花床に花がつくので花床を摘み取らないことだ。 日蔭を好み5℃程度の寒さには耐えるので冬は室内か温室が必要。あまり暗すぎると花付きが悪くなる。 |
全国に分布するオオバギボウシの変種である。 屋久島で低地に生育するのはオオバギボウシで、高所の岩場に生育するのはヤクシマギボウシである。 根茎が太く、葉は下部に群がってつく。 40cmほどの花茎に多くの花が横向きにつき、下から順に1日に1〜2個づつ咲く。 |
葉の基部につく球形の葉がムギに似ているので、ムギランの名があり、深い樹林内の幹や岩に付着するするので、ミヤマ(深山)ムギランという。 ムギランは葉が丸っこく、白い花を咲かせるのに比べ、葉が長く赤花を咲かせる。 花はいずれも6〜7月頃で、7〜8cmと小さく可愛い。 |
花の形が【大】の字の形に下の花弁2枚が長い。 ユキノシタの仲間には、こんな花形が多い。 屋久島には葉の基部が心形(ハート形)になるヤクシマダイモンジソウと、くさび形になるヒメウチワダイモンジソウの2タイプがある。 いずれも固有の品種で、標高1000m以上の明るい湿った岩上にコケ類と共に生えている。 花期は7〜10月頃。 |
| オオゴカヨウオウレン (キンポウゲ科) |
ヤクシマモジスリ (ラン科) |
ヤクシマタツナミ (シソ科) |
ヤクシマゼキショウ (ユリ科) |
 |
 |
 |
 |
| まだ残雪が残る早春の3月、暗い林内の苔の上に純白の梅の如き花が咲く。 標高500〜1000m前後の林内に生える特産種。 葉が5つに切れ込み、ゴカヨウオウレンより大きいのでその名がある。 黄連の仲間と同様、胃薬となる。 |
屋久島の高所に自生する多年草。 モリズリの矮小品で花茎の高さ約13cm、葉の幅4mm、長さ4cmほどで、根元に広がっている。 花は20〜25個つき、色は赤紫で直径1.5mmほどである。 |
標高1000mを越える辺りで、歩道脇によく見られる。 高さ5cmほどの茎に、その割に大きい、長さ15mmほどの青紫色の花を数個咲かす。 和名は、屋久島産の立浪草の意味。 花の作りが北斎の描く波頭に似ている。 花期は7〜11月。 |
標高900m以上の苔のついた花崗岩の上に育成する。 葉は、幅3〜5mm、長さ5〜10cmで、まとまって多数出る。 成長の良いものでは、長さ約15cmの花茎に白く美しい花が多数咲く。 |
| ヤクシマアザミ (キク科) |
ヤクシマシャクナゲ (ツツジ科) |
ヒカゲツツジ (ツツジ科) |
サクラツツジ (ツツジ科) |
 |
 |
 |
 |
| 登山で草地に腰を降ろすとチクリと刺す。 その刺の鋭いこと。 標高1500m辺りから山頂近くまで分布し、8〜9月にノアザミのような花を付ける。 草丈10〜30cm。 葉身が狭く、刺だらけで強い感じがする。 種子島にも分布すると言われるが疑問。 |
世界3000種の中で最も美しいと言われる屋久島の名花。 上屋久町の町花でもあり、島民の心の花でもある。 常に上向きに付く小型の葉、葉裏の綿毛が極めて多く、花は真紅・ピンクから純白へと変わる。 5月末〜6月中旬、1300m以上の山々を美しく彩る。 |
淡黄色の花を咲かせるツツジ。 花期は4〜5月。 屋久島では標高1000m付近から潅木帯まで分布する南限種。 低木であるが時に2m以上にもなり、岩隙や樹上に養生する。 割合と日蔭に生えるのでその名があるが、雲霧帯では樹上や岩上の割と日当たりのよいところに生え、屋久島の古木に彩りを添えてくれる。 ハイヒカゲツツジは山頂近くの岩隙に生える矮小種で、樹高10cm程度。 花も小型で固有変種とされている。 |
図鑑では「高さ1〜2mの常緑低木」と書いてあるが、径20cm、高さ6〜7mにもなる木である。 島ではカワザクラと呼ばれ、低山地から山頂近くまで分布している。 花は4〜6月まで、低山から咲き登る。 ピンクの可憐な花は多くの人に親しまれ、屋久町の町花でもある。 |
| リュウキュウエビネ (らん科) |
オダクミツツジ (ツツジ科) |
シシンラン (いわたばこ科) |
ヤクシマコオトギリ (オトギリソウ科) |
 |
 |
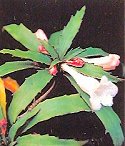 |
 |
| 屋久島には、春エビネは少なく、多くがツルラン(白)である。 それらのなかに時折、臼紅紫色〜濃紅紫色の花をつけるものがある。 これがリュウキュウエビネで、オナガエビネとツルランの交雑種と言われる。 7〜9月頃に咲くので総称して夏エビネとも呼ばれる。 園芸用として人気が高いが、大量増殖できないのが難点。 |
葉が極端に細いサツキ。 サツキの花は合弁花でロート状になっているが、離弁、あるいは、離弁状に深く切れ込み、花弁も細いのが特徴。 屋久島の小田汲川で発見された品種だが、残念にも原産地には一本もない。 だが、今、島内で増殖中。 今後増えるであろう。 |
「ラン」と名づいているが、ランの仲間ではない。 樹上の苔の上に養生し、養生ランに似ているからであろうか、茎は半ばつる性で苔の中を這い、根を広げている。 葉が厚く美しく、花も草丈の割には長さ3〜3.5cmと大きく、淡いピンク色、ゴイシジミ(シジミチョウ科)の食草になるという。 花期7〜8月、 山野草として愛好される植物の一つ。 |
屋久島の固有変種。 ナガサキオトギリの矮小品。 高層湿原では、ミズゴケに混じって咲き、人目につきやすいが、その前後の登山道にも見かける。 茎は長さ約10cmで、やや地を這うように伸びていて、長さ約8mmの長楕円形の葉をつけ、明点が密に散在する。 黄色い花が6月頃から咲く。 花期6〜8月。 |
| オオタニワタリ (チャセンシダ科) |
アマクサシダ (いのもとそう科) |
ボウラン (らん科) |
 |
 |
 |
| 『昔は多かった』と言わねばならないのが心苦しいそうだ。 葉は生花として人気が高く、広葉樹林が杉林となったこともあって激減した種のひとつ。 紀伊半島まで分布しいるが、本土では数少ない熱帯、亜熱帯の植物。 もっと増やす必要があろう。 |
葉に毛が無く、光沢があり、立姿も見た目に美しいシダ。 観葉植物として適している。 葉を注意して見ると、上側の裂片が欠けているのが特徴。 関東以西太平洋岸、四国九州に分布するが、天草で発見されたことにより、その名がある。 オオアマクサシダはもっと大型で、70cm〜80cmになるもので、屋久島を北限とする。 |
見ての通り、葉も茎もまったくの棒状。 低山のクスやシイ、タブノキなど、樹皮の荒い幹に養生する。 近年はそれらの樹木の減少と共にボウランを始めとする養生植物も少なくなった。 花は7〜8月、1cmよりやや長い黄緑色で唇弁に濃紫色の斑紋がある。 美しいと言える花ではないが、棒状の草姿がおもしろい。 |